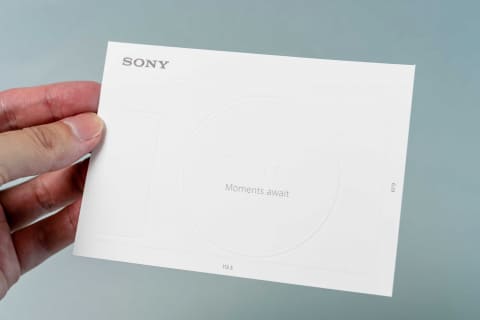ニュース
ソニーのレンズ一体型カメラ「RX1R III」実機触ってきた。作例つき
2025年7月17日 16:54
ソニーは7月15日に発表したフルサイズセンサー採用のレンズ一体型コンパクトカメラ「RX1R III」(型番:DSC-RX1RM3)。8月8日の発売に先駆けて実機に触れてきたので、外観と作例をお届けする。
RX1R IIIは、2015年11月に発表、'16年2月に発売した「RX1R II」の後継機。価格はオープンで、市場想定価格は66万円前後。ソニーストアでは7月23日10時から予約を受け付ける。
前モデルで高い評価を得ていた一体型「ZEISS ゾナーT* 35mm F2」はそのままに、フルサイズのイメージセンサーは有効約4,240万画素のExmor Rから、有効約6,100万画素のExmor Rに強化。画像処理エンジンもBIONZ Xから、最新のBIONZ XRとなったほか、ミラーレスカメラ「α」シリーズでも採用されているAIプロセッシングユニットも搭載した。
また従来モデルではポップアップ式だったEVFは固定式になったほか、チルト式だった背面液晶も固定式に変更されている。ソニー担当者によれば、どちらも使い勝手を考慮した変更とのこと。また液晶の固定化は本体の軽量化にも貢献している。
筆者は普段、ソニーのレンズ交換式ミラーレスカメラではもっともコンパクトな「α7C」をメインカメラとして使っている。同じフルサイズセンサー採用カメラだが、実際にRX1R IIIを手に持ってみると「軽い!」と思わず声が漏れてしまった。ちなみにα7Cの重さはバッテリー/カード込みで約509g、RX1R IIIは同約498g。
グリップについては、α7Cのほうがよりしっかり握り込める形状だが、RX1R IIIは本体が軽量なこと、グリップに新テクスチャーを採用していることなどもあり、とくに持ちにくさは感じなかった。
オートフォーカス(AF)は、AIプロセッシングユニットを採用していることもあり、高速な被写体認識を実現。人物の瞳はもちろん、今回はぬいぐるみだったが動物の瞳も素早く認識していた。
動画撮影は最大4K/29.97pに対応。手ブレ補正は電子式で「アクティブ」に対応しているが、「アクティブ」にすると、画角がクロップされる。またカメラを構えるとUIも縦表示になるので、ショート動画/縦動画も撮影しやすい印象だった。
なお、このRX1R IIIは7月18日からソニーストア銀座/札幌/名古屋/大阪/福岡天神で先行体験・展示がスタートする。
「変わらない良さ」と表現を広げる「さらなる進化」。製造は幸田工場
ソニーの担当者は、前モデルのRX1R IIについて「ZEISS ゾナーT* 35mm F2のレンズ一体型で、約4,240万画素のフルサイズセンサーを搭載し、それが約515gの小さなボディに収まっている、このユニークなキャラクターが、今でも多くのフォトグラファーの方々に愛用頂いている理由」と説明する。
「振り返ってみると(シリーズ初代モデルの)RX1は、ソニーで初めてカメラグランプリで賞を獲得したエポックメイキングなカメラで、そのあとに(ミラーレスカメラの)α7シリーズが誕生し、この10年間でα7R Vまで進化してきました」
「そんな2025年の今だからこそ、『新しいRX1が欲しい』という声を多くの方々から頂いていました。αで培ってきたソニーの技術をふんだんに詰め込んだ、新しいRX1を作ることができたと考えています」
「(RX1R IIIで)我々が大切にしていきたいポイントはふたつ、『変わらないRX1の良さ』と『さらなる進化が撮影表現を広げる』ということです」
10年を経てのモデルチェンジとなったが、採用するレンズは前モデルと変わらずZEISS ゾナーT* 35mm F2のまま。これについては「ZEISS ゾナーT* 35mm F2というレンズは、非常に多くのお客さまから高い評価を得ていました。『このレンズが良いんだ』という声を頂いていたのが背景です」と説明する。
「やはり美しい描写とコントラスト、中央部の解像度と、そこからのなだらかなボケなど、非常に(描写が)美しいレンズだという声を頂いていました。なにより35mm F2という画角・F値もポートレートやスナップ撮影などにとても使いやすいものだと思います」
「これはレンズ一体型だからこそできる光学系の影響が大きいと思っています。センサーの目の前に後玉が来るような光学系になっていて、そのなかに非球面レンズの採用や、ツァイスのT*コーティングなどを施すことで、より解像度とコントラストの美しさを高めることができていると思っています」
そして「このレンズの良さを最大限に引き出すのが、今回刷新したCMOSセンサー」だと説明。最新のαシリーズで実現している忠実な色再現性は踏襲しつつ、ISO感度は常用ISO 32000、拡張ISO 102400と、α7R Vや、α7CR同等を実現し、15ストップのダイナミックレンジも実現した。
オートフォーカス(AF)性能も、α7R Vとα7CRと同等だとしつつ、「従来モデルから測距エリアが広くなり、暗い部分でも動作するようになった」のが強み。「35mmという画角ですし、“動きモノ”を撮るカメラではないと考えていて、どちらかと言うとスナップ撮影、ポートレート撮影で『パッと撮りたいものを撮れる』ような速写性がキーポイント」だとした。
新機能として画角を35mm、50mm、75mm相当にワンタッチで切り替えられる「ステップクロップ撮影機能」、カメラ単体で思い通りの表現ができるクリエイティブルックに、落ち着いた発色のノスタルジックな表現ができる「FL2」、クリアな発色の軽快な表現が可能な「FL3」を採用している。
バッテリーは主にコンパクトデジタルカメラで採用されているXバッテリー(NP-BX1)からαシリーズで使われるWバッテリー(NP-FW50)に変更された。センサーや画像処理エンジンの強化などにより、システム全体での消費電力量は増加しているものの、バッテリー強化も相まって、最大撮影可能枚数は従来の背面モニタ使用時約220枚/EVF使用時約200枚から、モニタ使用時約300枚/EVF使用時約270枚に強化された。
EVFは従来のポップアップ式から「速写性に寄り添うために」固定式を採用。最終光学面からのアイポイントも、従来の約19mmから約22mmとなっている。
これら性能の強化、バッテリーの大型化が行なわれたにもかかわらず、本体の軽量化を実現。従来のバッテリー/カード込み約507gから、同約498gに軽量化されている。これには背面液晶の固定化(従来はチルト式)も影響しているとのこと。
カメラの製造は「国内の幸田工場で製造していて、クリーンルームでひとつひとつ、レンズとボディ、センサーを手作業で調整しながら製造しています。この繊細さ、設計があるからこそ実現できている画質だと思っています。(同社レンズ交換式ミラーレスカメラでもっともコンパクトな)α7CRに35mm F2のレンズを装着した状態とは、まったく別のカメラだと考えて欲しい」と語った。
そのほか、グリップに新テクスチャーを採用し、外装塗装も「まったくαと違う」新開発のアイアンブラック塗装を使うなど、ユーザビリティも強化されている。