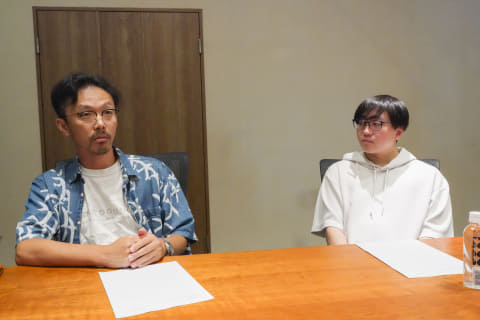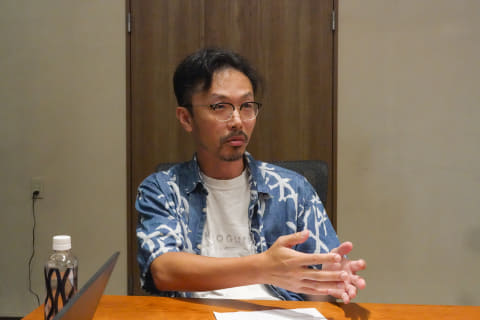ニュース
山崎貴監督の「白組」映像制作にもmocopi!! 実写映画のプリビズ映像に活用
2025年9月1日 08:00
ソニーの小型モーションキャプチャーデバイス「mocopi」。6点から12点のセンサーを装着して、VRChatやVTuberなどの3Dキャラクターを動かせるコンシューマー向けのデバイスだが、ゲームやMVなど3DCGを使ったクリエティブな現場での使用事例も増えてきている。
弊誌でもカヤックアキバスタジオのアニメ表現を取り入れたMV制作、コジマプロダクションのゲーム開発での活用事例について取材してきたが、今回は初の実写作品での活用事例を紹介する。
実写映画などのVFX制作を手がけ、映画「ゴジラ -1.0」の山崎貴監督も所属する映像制作スタジオ「白組」に潜入し、VFX スーパーバイザー/CGアーティストの植木孝行氏とVFXアーティストの佐藤昭一郎氏に話を聞いた。
mocopiはプリビズ(事前映像)に活用! 演技のイメージ共有がより詳細に
一般的な実写映画の制作の流れは、以下のようになる。
- 企画の立ち上げ
- 脚本やそれを元にした絵コンテ制作
- 絵コンテをもとにこれから撮る映像をイメージしやすくためのプリビズ(事前映像)制作
- プリビズからさらに計画を立てて撮影
- 撮影された映像に対してCGを当てはめていくVFX作業
- 編集やグレーディング(色の調整)、音楽やセリフ入れ
そしてmocopiを使用しているのは、「プリビズ制作」の部分。プリビズは、実際の撮影に臨むに当たって、スタッフ陣や役者の人たちとより明確なイメージを共有するために作る映像のことで、実写やCGを織り交ぜたざっくりとした映像になるという。
植木氏(以下敬称略):映画監督の山崎が弊社の所属で、脚本も担当していることが多いので、かなり初期の段階から僕らもどのようなことをやるのか聞きながら話が進んでいくことが多いです。脚本が作られて、それを元に絵コンテも山崎が描いていきます。
絵コンテはどんな話をどのように進めるのか、ということを色々な人に見せる「意識の共有」をするためにつくられるものですが、1枚の絵よりも動画になっていた方がさらに伝わりやすくなるという理由で、プリビズ映像が作られます。
そして、このプリビズ映像の制作から僕らが本格的に参加していきます。プリビズはラフな映像ですが、たくさんの尺が長い映像を作らなくてはならないので、そこでmocopiを活用しています。
僕も佐藤もアニメーションを付けられる方なので、メインのキャラクターなどは自分で手付けした方が良い、みたいなこともあるのですが、例えば爆発が起きるシーンで、逃げながら爆発の影響で倒れる人々、みたいな場面があるとします。そのような部分までアニメーションを付けるほど労力を掛けられないので、従来は身振り手振りなどの無い人形がポンポンと跳ねてピューンと吹っ飛んでいくような簡単な映像になっていました。
それがmocopiを使うことで、自分たちで演技をして、どれくらいのリアクションや飛び方なのかをより表現できるようになりました。
以前はスーツ型のモーションキャプチャーを使用していた植木氏のチーム。キャプチャーの性能ではスーツ型の方が有利だと思われるが、mocopiの“手軽さ”に魅力を感じたのだという。
植木:スーツ型のモーションキャプチャーを使用していたときは、「じゃあ明日撮ろうか」と撮る動きなどをメモしたりと色々準備をした上でキャプチャーに臨む、といった感じでした。mocopiは圧倒的に手軽になったので、逆に「面倒くさいから今撮っちゃえ」と思いつきでパッと撮れてしまう手軽さが魅力です。
スーツ型は汗だくにもなるので、スタッフ間で使い回すのも抵抗があったりなどしましたが、mocopiはデスクの後ろの狭いスペースでキャプチャーできて、12カ所にバンドを着けるだけなので、誰でもパッと使えます。
佐藤:着けるのも体感1分くらいですしね。
植木:スーツ型だと意気込んで大がかりな感じになるので、撮るモーションがリストから漏れていたりすると、手間を掛けて撮り直したくないので、諦めて手付けで作ってしまうということも多々ありました。
ほかにもiPhoneを数台使ってスキャンするという方法も試しましたが、スペースを取らなければいけなかったりして、結局スーツと同じように準備して撮影する必要がありました。
そんなときに、三軒茶屋スタジオのスタッフがmocopiを購入していて、それを貸してもらったときに手軽で良いなと。mocopiの体験会にこちらから伺い、本格的に導入が決まりました。
最初に触ったのがセンサー6点の状態だったので、この手軽さでもう少し精度が良ければと思っていたところ、体験会で12点の精度を確認して、これなら使えるぞと。XYN Motion Studioもそこで内容を確認し、合わせて導入することになりました。
XYN Motion Studioは、mocopiと組み合わせたモーション制作の統合アプリ。キャプチャーからモーションデータのタイムライン編集、クラウド保管などが行なえる。
複数のモーションデータを滑らかに繋げる中間モーション自動生成機能を搭載しており、例えば、「ゾンビに追われて走って逃げながら、隣で転んだ人を起こしてまた走る」というシーンを「走る」「人を起こす」「走る」の3つのモーションデータを後から繋げても違和感ないモーションデータにできるという。
植木:デスクの後ろで、思い立ったときに撮り始めるのですが、モーションが撮れればいいので、端から見ると黙って大きな動きをしている人になってしまって。「なにやっているかわからないから、セリフは言ってくれない?」と周囲に言われることがあります(笑)
植木氏と佐藤氏は、mocopiで撮影したモーションデータをベースに調整する形で活用しているそうだ。インタビューに同席したソニー mocopiプロダクトマネージャーの南翔太氏は、このデータ活用の点で、保存形式や編集ソフトへのスムーズな移行方法などの細かなフィードバックを受けたという。
欲しい機能はやはり“精度向上”。将来的に本番でも使いたい
1月からmocopiを使ってきた植木氏と佐藤氏に、映像制作の現場視点で欲しい新機能についても聞いてみた。
植木:欲しい機能は、カメラキャプチャーですかね。今のmocopiではどうしても足周りが少し弱いので、画像と一緒に補完しながらより精度を高めてもらえるとすごく助かります。
あと上半身用に13点目が欲しいですね。胸にもセンサーがあると、肩を落として「はあ、はあ、」と息を整えているような動きがうまく撮れないんですよね。
佐藤:服の上から着ける部分だと、動いているとバンドが落ちてきてしまうことがあったので、滑り止めが欲しいです(笑)
肩が上がる、胸が開くといった動作はまだまだ課題となっているようだが、mocopiチームもセンサーの個数を増やさず、手軽さを保ったまま表現を広げていくよう取り組んでいるという。バンドについても、手首足首や腰などのセンサーをなるべく身体に直接巻くことで、安定度が上がるとのことだ。
こうした現状の課題を解決したら、本編に使われる本番のアニメーションにも採り入れたいという。
佐藤:精度が今以上に高くなって、本番のアニメーションにも活用できるようになったら、mocopiをメインに、ちょっと手付けで修正する、みたいな感じで、最前線で使えるくらいになったらもっと便利だと思います。
植木:本番で使うようなモーションキャプチャーは、しっかりした設備で撮ります。そうすると、やはり後になって、あの動き忘れていたとか、やはりあの動きも欲しかった、このパターンも欲しかった、みたいなことは多々あります。そこでもmocopiが活躍してくれたら、もっと映像の幅が広がって良い物が撮れると思います。
山崎貴監督のコメント
今回のインタビューには参加できなかった山崎貴監督より、実写映画でのmocopi活用についてのコメントも到着した。
例えば、逃げている人たちのモーションをmocopiでキャプチャすると、そのシーンのシミュレーションがより精細にできるので、本当に助かっています。
mocopiをプリビズ(事前映像化)で活用することで、登場シーンが少ない場合でも、セット制作の可否を具体的に判断できます。工数の削減にも大いに貢献している印象がありますね。
自分が起こしたテキストイメージをプリビズ内でmocopiを使って表現し、それを可視化できると、みんなが撮影シチュエーションやアウトプットのイメージを共有できるのです。
VFXでの撮影では予想ができないところがあるので、プリビズが必要ですが、芝居はその場での撮影になります。
プリビズの作業次第で制作コストが大きく変わるからこそ、プリビズはとても大事なんです。
皆が必要最低限の作業で済むようになるのも、非常にありがたいですね。