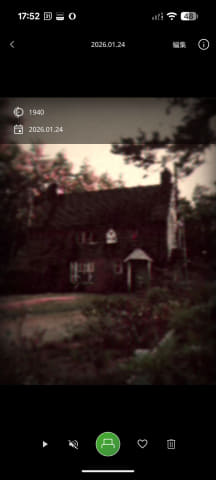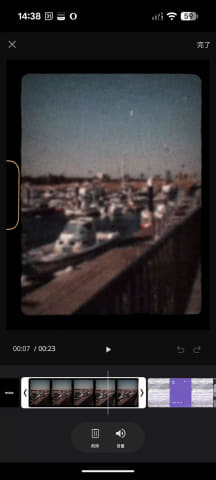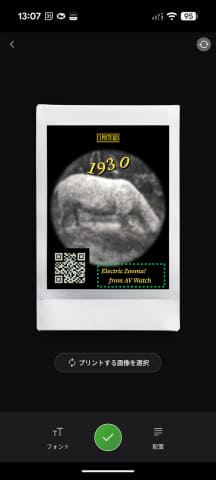小寺信良の週刊 Electric Zooma!
第1207回

時代を捕まえるカメラ。富士フイルム「instax mini Evo Cinema」が示す動画の可能性
2026年1月28日 08:00
初の動画対応機登場
富士フイルムの「チェキ」と言えば、その場で写真がプリントできるインスタントカメラとしてかなりメジャーな存在である。アイドルとの2ショット写真などに利用されていることで有名だが、ネットに安易に出回らない対策として、あるいは世界に1枚しか存在しない価値として、「アナログの紙焼き写真」が評価された結果だ。
一方で同じチェキシリーズでも、デジカメのように一旦画像をメモリーに保存し、選んだ写真のみをプリントできるというハイブリッドカメラもある。これも「mini LiPlay 」と「mini Evo」の2シリーズ展開となっているところだ。
そんな中、動画を撮って渡せるという新コンセプトのカメラ「instax mini Evo Cinema」(以下Evo Cinema)が1月30日に発売される。市場想定価格は5万5,000円前後となっている。
静止画のほか動画が撮影できるだけでなく、様々な時代をイメージしたエフェクトを搭載、本体脇の「ジダイヤル」で年代が選べるようになっている。年代は1930年代から2020年代までの10段階、すなわち動画100年の歴史がエフェクトによって表現されるというわけだ。
今回はいち早く評価機をお借りすることができた。時代を切り替えるという新コンセプトのカメラを、早速試してみよう。
8mmフィルムカメラを彷彿させるデザイン
チェキといえば一般的にはもっこりしたやや大型の縦型カメラを連想するところだが、Evo Cinemaは全く異なっている。富士フイルムは1965年に8mmフィルムカメラ「フジカ シングル-8」を商品化しているが、そのスタイルを継承した縦型スタイルとなっている。
正面にレンズ、背面に液晶画面を配して、縦方向にグリップして後ろから覗き込むという撮影スタイルだ。また接眼で撮影できるよう、ファインダーアタッチメントも付属している。機能的には動画+静止画+プリンタの3-in-1で、このスタイルはinstax初となっている。
まず光学部から見ていくと、レンズの焦点距離は35mm換算28mm単焦点レンズだが、デジタルズームに対応している。絞りは2.0固定だ。AFはシングルAFだが顔認識が可能。撮影可能範囲は最短10cmから無限遠となっている。
1/5型CMOSの原色フィルターで、有効画素数は約500万画素。よって記録画素数は、静止画で1,920×2,560ピクセル、動画撮影は600×800ピクセルとなる。ただ高画質モードを選ぶと、ジダイヤルが2020の時のみ、1,080×1,440ピクセルの動画も同時に撮影される。つまり2020モードが本来の標準画質ということだろう。なお動画撮影は24pで、1ショットは最大15秒に限定されている。
レンズ周りのリングは、ジダイヤルによるエフェクトの強さを可変するためのものだ。全部で10段階あり、ダイヤルにはクリックがある。ただ段階は液晶画面内のメーターに表示されるだけで、ダイヤルではわからない。ダイヤル上に数字表記があってもよかったかもしれない。
レンズの上にはLEDライトと、おそらく測距用と思われるセンサー、小さいミラーがある。ミラーは自撮りするときにアングルが確認できる。専用アプリを使用すれば、ライブビューの確認やリモート撮影も可能だ。
レンズ下に撮影ボタンがある。これは押している間だけ録画する方式と、一般のカメラ同様押して録画/再押しで停止方式に切り替えられる。
その下には充電用USB-C端子がある。ここをパソコンなどと接続しても、メモリーがマウントされるわけではない。その下にmicroSDカードスロットがある。内部メモリーもあるが、写真で約50枚、動画で10本程度しか入らないので、何らかのカードは挿入した方がいいだろう。また動画をパソコンなどに取り込みたい場合は、SDカード経由で取り込むしか方法がないので、パソコン編集を併用したい場合は注意が必要だ。
左側面には電源ボタン、写真と動画の切り替えスイッチ、その下の四角いアイコンはジダイヤルエフェクトでファインダー上に表示される文字情報ごと記録するか、動画のみ記録するかの切り替えスイッチだ。文字情報のフレームは「記録メディアや再生デバイスを連想させる」もので、各時代のカメラのファインダーでの見た目を表現したものである。
フィルム巻き上げダイヤルっぽく見えるのは、写真プリント用のトリガーだ。半回転しか回らないが、1度回して印刷モードに切り替え、もう一度回して印刷というアクションになっている。うっかり回して印刷されてしまうことがない。
後ろ側にあるのがジダイヤル、その下のプラスマイナスレバーがズームだ。ズームは無段階ではなく、ステップズームだ。
背面にはメニュー、戻る、OK、再生ボタンがあるほか、メニュー選択に使うダイヤルがある。右側はチェキフィルムを装填するスロットだ。
付属アクセサリとしては、先に述べたファインダーアタッチメントがある。視度調節はないので、単に接眼して見えるだけである。
また底部に取り付けるグリップもある。通常の状態では中指から薬指ぐらいまでしか指がかからないが、グリップで拡張すると小指まで使ってしっかりグリップできる。
時代が遡れる「ジダイヤル」
本機最大のポイントは、10年ごとの時代の映像をシミュレーションした、ジダイヤルエフェクトを搭載したことである。
これまでも、いわゆるオールドスタイルのようなデジタルエフェクトを搭載するカメラはあったが、それはいつ頃の映像を象徴したものなのか説明されたことはなかった。こうした様々なオールドスタイルのエフェクトを、時代ごとに分類したという点で、非常にユニークだ。
ではまず各時代でどのような映像になるのかを調べてみよう。静止画と動画どちらでも同じ画質だが、動画の方がわかりやすいかもしれない。ファインダ情報は焼き込みアリに設定している。
1930年代は、今からざっと100年前ということになるが、モノクロでフィルム傷や画面の縦揺れがあることから、フィルム撮影の様子をシミュレーションしたものと思われる。コマが大きく飛ぶのは、手ブレを検知してその部分を飛ばしているようである。このコマが飛ぶという表現は、フィルムのパーフォレーションの欠損などが原因で、テレシネ、あるいはフィルム上映中にコマの位置がズレることで生じる現象である。
1940年代はカラーになっているが、RGBがズレているような映像表現になっている。カラーフィルムで撮影した段階では原理的にはRGBはズレないので、これはテレビ放送向けにテレシネした際に、RGBの分光がズレた状態を表しているものと思われる。
カラーテレシネ装置は、フィルムを透過した光をRGBに分光し、それぞれを撮像管で撮影するという仕組みになっている。現在のカラーテレシネはRGBをいっぺんに読み取るが、初期のカラーテレシネではRGBをそれぞれ時間差で読み取るといった構造の装置もあったようだ。そこでRGBの撮像管の位置がきちんと合わないと、このようにRGBそれぞれの映像の位置がズレた映像になってしまう。
ただこれは、歴史的には正しくない。カラー放送の開始は米国でさえ1953年であり、カラーテレシネが登場したのはおそらく1950年代後半から1960年代ではないかと思われる。
1950年代は、モノクロで周辺が丸い映像となっている。これは当時の日本の放送はまだ白黒であり、白黒テレビのブラウン管表示をシミュレーションした表現だろうと思われる。カメラが動くと横方向にギザギザでズレてしまう様子は、低解像度インターレース撮影特有の様子を再現している。
1960年代はカラーだが、フィルムグレインが見られる。これはカラーフィルムで撮影したものをシミュレーションしたものと思われるが、パーフォレーション欠落によるコマ飛びはない。
1970年代は、ビデオっぽい映像になっている。70年代になるとニュースはフィルム撮影からビデオ撮影に変わっていった。これをElectronic News Gathering(ENG)と呼ぶ。また画面周囲が丸く囲まれていることから、ENGのニュースをブラウン管で見ているような状態をシミュレーションしたものと思われる。
1980年代は、日付がオレンジで焼き込まれ、フィルムグレインが見られる。80年代はENGもUマチックからベータカムに変わった時代であり、アナログながら画質的には進化したので、動画の世界ではこのような時代背景はない。おそらく当時主流だったフィルム型コンパクトカメラの写真的な画質を動画風にシミュレーションしたものと思われる。
1990年代は、画面が白っぽく日付もディザリングされていない白文字で表現されている。画面下には白いノイズが見られるが、これはアナログビデオヘッドのトラッキング調整がうまくできていない場合に見られる現象である。
画面右上にTBCという文字が見られるが、これはTime Base Correcterの略である。TBCはアナログビデオ信号の補正に使われる装置で、映像システムと同期する場合には必須だ。
TBCは時間軸補正以外に、ドロップアウト修正や同期信号入れ替えなどを行なうので、TBCを通してここまで映像は乱れるのは、技術的にはあまり考えられない表現である。
SPという表記が何を表しているのか判然としないが、おそらくVHSの標準速度モードを表しているのかもしれない。そう考えると1990年代は、VHSの画質をシミュレーションしたものと思われる。
2000年代の映像は、「P」の文字や「ISO AUTO」といった表記が見られるので、コンシューマのデジタルビデオカメラで撮影した映像をシミュレーションしたものかと思われる。1995年には家庭用DVカメラが登場し、2000年代にはかなり普及していくので、その当時の色味を再現したものだろう。
2010年代は、左上にLIVE、下にはスクロールバーや音量アイコンなどがあるので、YouTubeを象徴した映像ということだろう。色味は若干アンバー寄りで、若干懐かしい感じを演出している。
2020年代は現在ということになるので、本機の標準画質ということになる。色味もすっきりしており、解像度は低いがトイカメラのような低画質ではない。1縦横の構図位置を示すラインも見えるので、おそらくデジタルミラーレスを象徴しているのかもしれない。画質的にはもっとも綺麗にまとまっている。
これらのエフェクトは、それぞれの時代背景を正確に表しているわけではなく、あくまでも時代の雰囲気を表現したものと捉えるべきだろう。それぞれの時代ごとに、同じカメラワークでコンテンツを作ってみたが、「なんとなくそれっぽい」というだけで、十分楽しめる。
動画の編集と共有
動画は1カット15秒しか撮影できないこともあり、何らかのコンテンツを作るには編集が必要になる。本体内には編集機能はないが、専用アプリと本機をワイヤレス接続し、映像を伝送して編集することができる。
基本的にスマホアプリとの接続はBluetoothだが、画像転送の際には高速なWi-Fi接続に切り替わる。
転送された画像はなぜか並び順が撮影順ではなくバラバラなので、編集素材として把握しづらい。撮影日時順やジダイヤル設定順などにソートできる機能が欲しいところだ。現在使用しているのはまだベータ版なので、このあたりは今後改善されるだろう。
ライブラリで各映像の情報アイコンをタップすると、いつの時代設定で撮影されたものなのかが確認できる。ただ動画編集中の素材選択画面では情報アイコンが表示されないので、どのエフェクトで撮ったのか確認できなくなる。
あんまり時代をあれこれ入れ替えて使うものではないのかもしれないが、10種類もあると見た目でわかるようなものではないので、やはり編集中も時代の確認ができるとありがたい。
動画編集のやり方としては、一般的な動画編集ツールと大きく変わるところはないが、ビデオトラックは1つだけで、オープニングとエンディング以外はあまり装飾性がない。またアプリ内に読み込んだ動画はスマホ上のライブラリに書き出す機能もないので、別アプリで編集はできない。
もっともここでは、簡単に編集してチェキを利用して共有するという目的があるので、それでいいのかもしれない。
編集した動画はプロジェクトとして管理される。プロジェクトはチェキでQRコード付きでサムネイルをプリントできる。プリント後には自動で編集した動画がクラウドにアップロードされる。そのQRコードを読み込んだ別の人がクラウドへアクセスして、動画を視聴したりダウンロードしたりできるという仕組みだ。
アップロードした動画は、2年間保持されるが、それ以降は自動的に削除されるようだ。チェキを媒体とした動画共有というのは、なかなか楽しみがある。
編集が面倒な場合は、撮影ボタン設定を「長押しで撮影」にすると、「ボタンを押した間だけ録画」を何回か積み重ねて、15秒までの動画を作ることができる。つまり撮る時にすでに編集してしまうような感じだ。これはかつてのフィルム時代の報道撮影のやり方で、「順撮り」と呼ばれていたものだ。
例えば交通事故現場の報道だと、最初に交差点の全景、車両のぶつかった場所のアップ、車両全体、道路上の破片……といった具合に順番に撮影しておくと、現像して編集なしにすぐOAできる。ENGが普及する前なので、1960年代ぐらいの手法ではあるが、NHKの報道ではまだ70年代でも一部フィルム取材だったので、このような手法が使われていた。
総論
富士フイルムの製品なので、てっきりジダイヤルは各時代ごとのフィルムシミュレーションを行なうのかと思っていたが、実際にはコンシューマテレビやビデオのシミュレーションを行なうモードのようだ。それはそれで前例がないので、非常に面白い分類である。
電源ONはしばらく待たされるので、きびきび動く感じはないが、撮影スタイルといい15秒しか撮れない動画といい、いろんな意味で今風かつエモいカメラに仕上がっている。普通の家庭用カメラとは全く逆行するが、そこがまた面白いところである。
スマホアプリからクラウド利用は、多くのカメラメーカーがトライしたところだが、今一つうまく機能しなかった。それをチェキという媒体を経由して動画配布に使うというアイデアも、なかなか面白い。またアイドル界隈に多く利用されそうな機能だ。
2020年モードで撮影したりプリントしてみた印象は、「意外によく撮れる」。AFのおかげでピンボケも少なく、トイカメラとはレベルが違うものだと感じた。
instaxシリーズで唯一動画撮影に対応し、しかも写真もプリントもできることを考えたら、5万5,000円という価格はそれほど高いものではないように思う。