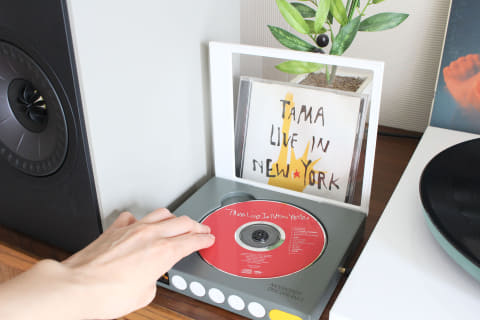トピック
レコードやCDと直結、KEF「Coda W」は“こじらせた僕ら”を点音源で包む同軸スピーカーだ
- 提供:
- KEF Japan
2025年10月31日 08:00
昔から好きで聴き続けている楽曲が、ことごとくサブスクで配信されていない現象に名前をつけたい。そんな時は、「いや別にフィジカルで持ってるから良いんだけどね」なんてプチ強がりながら、従来通りにCDやレコードを引っ張り出して聴くことに。音楽サブスク全盛の今、そんな経験をしたことのあるアラフォー以上の音楽ファンは、地味に多いと思う。
また、音楽配信で育ったからこそ、CDやレコードという物理メディアにグッとくる若者も増えている。どうせなら、手にしたCDやレコードを、音も、見た目も本格的なオーディオで聴きたいと思うのも、自然な流れだ。
でも、何十万円もする機器には手が出ないし、大きなアンプやラックを部屋に置くスペースもない。けれど、お手軽なBluetoothスピーカーでは満足できない。イイ感じのデザインで、アンプとかは不要で、そこまで高価ではないスピーカーが欲しい……。アラフォーも若者も、音楽ファンが今どき思うことは皆同じ。
そんな、こじらせた我々の心を「CDプレーヤーもアナログプレーヤーも、直接接続できるようにしといたよ」と優しく包み込むように登場したのが、KEFの同軸アクティブスピーカー最新モデル「Coda W」だ。
詳しい方は製品名を見てピンと来るだろうが、このCoda W、1970年代に登場したKEF“Coda”シリーズの名を受け継いでいる。当時、コンパクトで性能が高く、手の届きやすいスピーカーとして登場したCodaのスピリットを、現代のアクティブ構成で再解釈したモデルである。
価格は129,800円(ペア)。それなりの価格だが、詳しい仕様を知ると、“こじらせた僕ら”にとってはかなりコスパが高いスピーカーと言って良い。さっそく、その魅力に触れていこう。
端正でクラシカルなデザインに、現代のテクノロジーを内蔵
まず特徴的なのは、レトロな雰囲気のデザイン。カラーも豊富で、ヴィンテージ・バーガンディ、ニッケル・グレー、モス・グリーン、ミッドナイト・ブルー、ダーク・チタニウムから選べる。今回はニッケル・グレーを使ってみる。
見た目はオーソドックスなブックシェルフだが、中身は完全に現代仕様のアクティブスピーカーだ。
シンプルな箱型のキャビネットに、KEF伝統のUni-Q同軸ユニットを搭載している。同軸ユニットとは、低音用と高音用など、サイズの異なるスピーカーの振動板を、並べるのではなく、同じ軸上に重ねた方式のことだ。音が出る場所が1つになるので、スピーカーの理想である“点音源”を実現できるのがメリットだ。
採用しているのは第12世代Uni-Qを少し改良したもの。上位モデル「LS50」の5.25インチウーファーを使用し、ツイーターはCoda W用に最適化。各ユニット専用のアンプで駆動する。周波数特性は38Hz~20kHzをカバーする。
さらに、フラッグシップモデル「LS60 Wireless」に搭載されたDSPを基盤とし、音楽信号を最適化する独自アルゴリズム「Music Integrity Engine」も採用する。KEFのスピーカーとしては低価格なモデルだが、同社独自の技術がたっぷり投入されており、音のエンジニアリングカンパニーである同社の思想が、随所に感じられる。
そして内部仕様と同じくらい興味深いのが、そのコネクティビティ。音声入力はAUXと光デジタルのほか、USB-C、HDMI ARCを装備。
そしてさらに、フォノ入力(MM)も備えている。そう、Coda Wはフォノイコライザー内蔵型の同軸アクティブスピーカーなのだ。
フォノイコライザーとは、レコードの音を補正しつつ増幅する専用アンプのことで、レコードプレーヤーに内蔵されていることもあるが、非搭載の場合は別途用意しなければならない。しかし、Coda Wはそれをスピーカー側に内蔵しているので、様々なアナログプレーヤーを直接接続できる。また、RCAライン入力も別に備えているので、フォノイコ内蔵型のアナログプレーヤーも接続可能だ。
つまりは、「アナログプレーヤーもCDプレーヤーも、テレビやPCも、フィジカルメディアとの接続は全部Coda WがあればOK」というのが、最大の魅力である。なお、音声入力端子はRchのプライマリースピーカー側に装備している。
HDMI接続に対応するKEFのブックシェルフといえば、昨年登場したWi-Fi対応のヒットモデル「LSX II LT」(ペア137,500円)も同価格帯で記憶に新しい。しかし、それとは方向性が異なり、このCoda WはWi-Fi接続には非対応。
ただそのぶん、aptX Adaptive対応のBluetooth接続をサポートしており、スマートフォン/タブレットと連携した高音質ワイヤレス再生の便利さは、ちゃんと享受できるようになっている。ちなみに上述のフォノ入力を備えているのも、Coda Wの方だけだ。
天面のタッチコントロール部もスタイリッシュ。電源操作のほか、入力切替や音量調整など、基本的な操作は全てこの天面でパパッと行なえる。
なお、Bluetooth再生のみ対応ながら、実はKEFのコントロールアプリ「KEF Connect」からの操作にも対応していて、スマホからの音楽再生に慣れた感覚で便利に使えるのもポイント。
個人的には、「HDMI接続できて、Wi-Fiは非対応。そしてフォノイコは内蔵していて、しかもフォノ入力端子を切り替えではなく独立して搭載する」という仕様に、素敵なこじらせっぷりを感じてグッと来た。
このスペックを見て、「これは自分のために作られた同軸アクティブだ」と思う人、筆者と同じアラフォー以上の世代に、わりと多いのではないだろうか。
例えば、「今の住まいは設置スペースに限りがあるので、最小単位のシステム構成にしたい」と考える“オーディオ出戻り層”の人とか。はたまた、「アンプとかフォノイコとか正直難しそうだけど、それなりにアナログ再生を始めたい」と思っているCD世代・サブスク世代の人とか。
Coda Wは、そんな“現代のライフスタイルで本格派を求めたいニーズ”に、バッチリ応えてくるアクティブスピーカーだ。上述の通り、HDMI ARCとUSB-C入力を搭載し、テレビやPCと直結できることも、現代的ニーズへの対応力を後押ししている。
それでいて見た目は、クラシカルなブックシェルフ。“英国的伝統”の空気を纏うデザイン性のおかげで、電源を入れていない時に絵になるのもまたニクい。
フィジカルでしか聴けない音を、現代の点音源で味わう
ではいよいよ、Coda Wを使っていこう。せっかくなので、こじらせ40代の筆者としては、サブスク解禁されていないレコードやCDをメインに満喫してみたい。筆者宅ではまず、同じ英国ブランドであるRegaのアナログプレーヤー「Planar 2」(92,400円)と直接接続し、リビングにある本棚の上に設置した。
なお、Planar 2はフォノイコは内蔵していないが、標準でMM型の「Carbon」カートリッジを装備しており、Coda Wのフォノ入力と直接接続できる。
「ターンテーブル+スピーカー」だけのシンプルなセッティングは、リビングやワークスペースにもなじみやすくて良い。いずれも外観がスタイリッシュな製品で、“英国オーディオの品格”が空間を引き締めてくれるようだ。
手始めに再生するのは、坂本龍一「未来派野郎」(1986年)のLP。“サブスク解禁されていない名盤”の代表格と言えよう。当時、CD・LP・カセットの3形態でリリースされていたという点で、レコードからCD時代への移行期という時代性が感じられるタイトルでもある。
筆者の実家には、親が所有していた本作のCD盤があったので、個人的にはそちらの方がなじみがあるのだが、今回はせっかくCoda Wにアナログプレーヤーが繋げるので 、中古で購入したLP盤の方をピックアップした。
これをPlanar 2のターンテーブルにセットして針を落とすと、さっそく1曲目「Broadway Boogie Woogie」の冒頭で聴こえてくるのは、映画「ブレードランナー」のセリフ音声のサンプリング。無断使用されたというこの音声が鳴った段階で、いつも「サブスク解禁されないのは仕方ないよな」という気持ちになるわけだが、今回はそれより早く、ギッシリと芯のある低域のビートがガッと前に飛び出してきて、一気に意識が持っていかれた。
電子音と生音の境界を曖昧にするような、ある種の実験的ダンスサウンドが、Uni-Qドライバーの駆動でクリアに再生される。メイシオ・パーカーのサックスと鈴木賢司のギターを絡ませながら、鋭いリズムと共に我が家の17畳リビングを包み込むそれは、ノスタルジーに浸るより先に「超カッコイイ」と思わせるサウンドだ。
名曲「黄土高原」では、畳み掛けてくるエレクトリックピアノの透明感のある主旋律が、フュージョン的なテイストと相まって美麗に空間を漂う。筆者が個人的に教授作品で最も好きな「Ballet Mécanique」では、サンプリングされたカメラ音や時計音、ワウワウ暴れるギター、弾力のあるベース音など、質感の異なる音それぞれの位置付けがよくわかる。
総じて、「音」と「音楽」の境目をあらわにしながら洪水のように溢れるサウンドセンスが、明瞭かつダイレクトに耳に響いてくる感じだ。
よく言われる“レコードらしい音の厚み”を享受できると同時に、制作者がこの1枚に込めた音楽的な鋭さも生肌にビシビシ刺さるのが良い。当時、世界初のフルデジタルシンセサイザーだったヤマハ「DX7」のブライトな音色を、現代のサウンドでクリアに楽しむという点でもまた一興。
この勢いで、CDも聴いてみよう。再生に使用したのは、MoondropのポータブルCDプレーヤー「DISCDREAM 2」(実売約19,900円)。コンパクトでミニマムなデザイン性がCoda Wと好相性な1台だ。
サイズは小さいが、ドライブモーターやCDレーザーヘッドには、オーディオ専用モデルを採用。DACに、Cirrus Logicの32bit Master HiFiオーディオコーデックを搭載するなど、中身は濃いプレーヤーだ。
先ほどの Planar 2の隣にちょこんと置いて、Coda Wとライン接続する。セットしたCDディスクは、たま「LIVE IN NEWYORK」(1993年)。
イカ天バンドのアイコン的存在としても語られることの多い“たま”は、つい先日、CD音源のサブスク配信が大量にスタートしてネット上でも盛り上がっていたが、唯一のライブ盤であるこのタイトルは、そのラインナップに入っていない(2025年10月現在)。ファンとしては、たまの生感あるステージングを享受できる公式音源として、大事にしたい1枚である。
これをCoda Wで鳴らすと、たま楽曲の味であるアコギやピアノ、アコーディオン、ハーモニカ、桶など様々な楽器の音に精細感があって、楽しい。「お昼の2時に」の速弾きピアノの弾力や、「あたまのふくれたこどもたち」「お経」など、絡むようなギターが印象的な楽曲では、しなやかな弦の鋭さ、ジャカジャカと掻き鳴らされる軋み感も伝わる。
そして、「らんちう」のようなドロリとした曲は、大口径ウーファーによるどっしりした低域が生かされ、どっぷりと黒い墨に浸かるような世界観が再現されるのがとても良い。
全体を通して、アコースティック感のある低音の力強さが印象的で、石川浩司のパーカッションのドドドド、ズシンという迫力や、滝本晃司のベースのヌルリとした物理的な存在感が強く、改めてリズム隊の下支えがすごいグループだなと実感した。
ともすれば、色モノと勘違いされがちなバンドの“テクニック側の魅力”を、Coda Wが存分に表現してくれて最高だった。「堂々とこじらせたままで良いんだよ」と言ってくれているようで熱い。
「LSX II LT」と比べて分かる、“こじらせ世代”への包容力
Coda Wの実力を味わったところで、先ほども触れた同社の「LSX II LT」との住み分けについて、少し整理しておきたい。
というのも、両者は同価格帯なので「Coda WとLSX II LTはどう違うのか」「どちらを選べばいいのか?」という悩みがあるからだ。
ただ、2機種を並べてみると、LSX II LTの方が一回り以上コンパクト。デスクトップでパソコンの隣に置くような場合は、LSX II LTの方がよりスマートだ。また後述するが、筐体の大きさの違いはそのまま音質にも表れている。
先にスペック的なところを見ると、内蔵のUni-QドライバーはCoda Wが最新の第12世代、LSX II LTはひとつ前の第11世代を採用する。そして音声入力については、2機種とも共通して装備するのはUSB-C/HDMI ARC/光デジタルだが、それ以外の部分に明確な違いがある。
まずワイヤレス再生に関する仕様。上述の通り、Coda WがWi-Fi非対応でBluetoothだけに特化しているのに対し、LSX II LTはWi-Fiに対応で、単体でAmazon Musicの再生が行なえたり、AirPlay 2やChromecastなどのネットワーク再生機能をサポートしている。
一方で、Coda Wにしかないポイントは、これまで見てきた通り独立したフォノ入力を装備し、アナログプレーヤーの直接接続に対応すること。さらに、LSX II LTで省略されたAUX入力も装備し、上述の通り多彩なフィジカルメディアとの接続をカバーする。
ざっくり整理すると、「Wi-Fi対応のデスクトップスピーカーを探す」という入り口から辿り着きやすいのがLSX II LT。対して、「レコードやCDをシンプルに、でも音は本格Hi-Fiで楽しみたい」という入り口から入ったユーザーは、Coda Wの方に行き着くだろう。
このユーザーが辿るであろう道筋の違いが何よりも音に表れていて、両者を聴き比べると、筐体が大きいCoda Wの方が、より余裕がある再生を実現している。
決してLSX II LTが悪いわけではない。機能とサイズ、音質のバランスから言って素晴らしいモデルで、設置スペースが狭かったり、聴く距離が近いのであればLSX II LTがオススメだ。
一方でCoda Wには、ある程度の距離から、ゆったりとHi-Fi的なサウンドを聴きたいという人を満足させるスケール感がある。
あと余談だが「なるほど」と思ったのは、Coda WもLSX II LTもHDMI ARCを搭載すること。従来のオーディオ再生部分では、“ネットワーク”と“フィジカル”で対応の分かれた両者が、むしろ“テレビとの接続”の方を共通項とするのは象徴的だ。
技術的・科学的なアプローチを時代のニーズに合わせて行なってきたKEFの、ブレない姿勢を感じると同時に、今の時代性を垣間見た。
「これは自分のための同軸アクティブだ」と思ったあなたへ
自宅で一通りCoda Wを使用して筆者が改めて感じたのは、ネットワーク再生に慣れた今こそ、あえて“繋ぐ・触れる味わいがある”ということだった。今どきの“フィジカルメディア×アクティブスピーカー”の楽しさを、たっぷり味わわせてくれるのがCoda Wだ。
音楽サブスク全盛時代の今、「自分こじらせてるな」と思う方ほど、Coda Wの音と見た目のバランスには心を掴まれるのではないか。「これは自分のために作られた同軸アクティブだ」とピンと来たら、きっとその感覚は信じて良い。
東京・青山にある直営店KEF Music Galleryでは、今回使ったCoda WやLSX II LTを実際に見たり、試聴もできるとのこと。試聴予約をすれば、じっくり試聴が可能なので購入を検討している方にはおすすめです。
KEF Music Gallery
https://x.gd/swy2p
Coda W製品ページ
https://x.gd/O51rB
LSX II LT製品ページ
https://x.gd/XlobFt