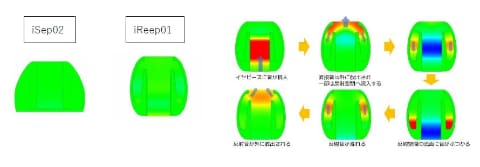トピック
Maestraudio傑作イヤフォン、進化してリーズナブルに「MAPro1000 II」を聴く。EDM特化“Drop”も
- 提供:
- アユート
2025年11月6日 08:00
仕事柄、友人などから「有線イヤフォンで何かオススメある?」と聞かれる事がある。音楽の好みや予算で選択肢は多数あるため、悩ましい質問だ。そんな時は「1万円ちょっとしても構わないか?」と確認したうえで、幾つか候補を挙げる。その中に決まって入れるのが、Maestraudioの「MAPro1000」だ。
理由は3つある。14,300円と、そこまで高価ではないこと。それでいてモニターイヤフォンらしく、高解像度で素直、全体のバランスも良好なサウンドを聴かせてくれること。そして、筐体がコンパクトかつ軽量で、装着しやすいこと。これらを満たしているので、多くの人がオススメしやすいわけだ。
そんなMAPro1000に、進化モデルが登場したとなったら、聴かないわけにはいかない。モデル名はズバリ「MAPro1000 II」。11月1日に発売されたばかりで、価格は13,200円(!)。なんと、この時世に、前モデルから低価格になっている。
Maestraudioによれば、「より多くの人に群馬発の音づくりを体験してほしい」(Maestraudioは群馬県高崎市に本社を置くオーツェイドのブランド)という想いから、苦労してこの価格を実現したそう。消費者にとっては、嬉しい限りだ。
「どんな音に進化したのか、さっそく聴いてみよう」と思ったら、さらに「MAPro1000 Drop」(14,300円)というモデルも同時に登場した。なんでもこのMAPro1000 Dropは、正統進化型のMAPro1000 IIに対して、EDMに特化させた“音楽ジャンル特化型イヤフォン”なのだという。こちらもどんな音なのか気になる。
さっそくMAPro1000 II、MAPro1000 Dropを両方お借りして、初代MAPro1000と聴き比べた。結論から先に言うと、その進化具合は、予想の遥か上を行っていた。
MAPro1000 IIの進化点
まず、MAPro1000 IIの進化点からチェックしよう。
初代MAPro1000は、小型軽量かつ軽快な装着感のモニターイヤフォンとして人気となったが、MAPro1000 IIでも形状やサイズは同じで、重量も軽量だ。カラーはFrost Mint、Shadow Crownの2色展開となっている。
ドライバーはハイブリッドで、10mm径のグラフェンコートダイナミックドライバーと、5.8mm径RSTというツイーターを搭載している。普通のイヤフォンとちょっと違うのは、このRSTという高域用ツイーターだ。
RSTはReactive Sympathetic Tweeterの略で、Maestraudio独自の圧電セラミックス技術を応用したパッシブ型セラミックコートツイーターだ。
“パッシブ”、つまり、自分で振幅するドライバーではなく、ダイナミックドライバーからの音波を振動板に照射する事で、ツイーターの振動を誘発させ、音を出している。
振動板の寸法や材質、支持方法などで音質をコントロールできるのが特徴で、これまでのMaestraudioイヤフォンにも、このRSTが使われている。そして、初代のMAPro1000から、MAProシリーズ用に開発された小型の5.8mm径RSTを搭載している。
ここまでは初代と共通する特徴だが、新モデルMAPro1000 IIでは、そこからサウンドをさらにチューニングし、進化させた。
具体的には、初代が持っていた「クリアで定位の良いフラットな音」を崩さず、そこに音の粒立ちと分離感を加えるために、オーディオ信号の接続部で使うハンダを、銀入り(Ag入り)ハンダに変更した。
銀の導電性の高さと音の伝送特性を高め、微細な成分の再現性が向上。情報量だけでなく、聴感上の中域から高域の空間表現も改善。見通しの良さも進化したそうだ。
それ以外にも、小さなチューニングを何度も繰り返し、進化させていった。
Agハンダは材料として高価なものだ。それを採用しつつ、価格を抑えるため、生産工程の合理化と組立手順の見直しも徹底。生産効率を高める事で、Agハンダを採用しつつ、より手に取りやすい価格を実現したそうだ。
使い勝手の部分も進化している。
前述の通り、初代機と同様の小型軽量ハウジングを採用。耳道に沿うノズルの角度や、形状も重心バランスにもこだわり、イヤーピースだけでイヤフォンを支えずに、筐体形状で耳に固定。長時間使用でもストレスが少ないイヤフォンに仕上げている。
ケーブルは着脱可能だが、MAPro1000 IIでは従来のMMCXコネクターから、特殊形状の接点補正ワッシャーへと変更。接続の信頼性を向上させている。コネクターカバーも左右判別がしやすい新タイプ(右=赤、左=青)になった。
なお、ケーブルは、高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。触ってみると被膜は柔らかく、取り回しやすいケーブルだ。
イヤーピースも刷新。硬度を再調整したスタンダードのシリコンイヤーピース「iSep02」が付属するほか、サラウンドイヤーピースとして「iReep01」も付属する。
iReep01は、ホームオーディオにおけるサラウンド技術やライブハウスの臨場感に注目して開発したもので、イヤーピース内部で効果的な反射音を作る事で、聴感上の遅延を感じ、広いサウンドステージと臨場感が得られるものだという。
MAPro1000 IIを聴く
MAPro1000 IIの音をチェックしよう。
その前に、初代MAPro1000の音を振り返る。付属の3.5mmケーブルを使い、DAPはAstell&Kern「A&ultima SP3000」を使って、主にQobuzのハイレゾ楽曲を中心に聴いた。
「藤井風/Prema」を再生する。冒頭から、サビが一気に展開する楽曲だが、コンパクトな筐体にも関わらず、音場はそれなりに広く、そこに色付けの少ない素直なサウンドが広がる。解像度も申し分なく、ボーカルとコーラスの重なり具合もよく見える。
一方で、輪郭を強調したような音ではなく、ナチュラルな描写で好感が持てる。ベースなどの中低域の厚みもあり、低い音から高い音までバランスも良好。全体として満足度の高い音だ。
細野晴臣のベースを聴くため、YMOの「TIGHTEN UP (Japanese Gentleman Stand Up Please!)」を再生。しっかりと低音が低く沈みつつ、音の輪郭はタイトでトランジェントは良好。非常に気持ちが良い低音だ。ただ、重さは感じるが、圧倒されるほどの重さや音圧の豊かさはない。
気になるところとしては、音場において、左右の広がりは良いのだが、あまり奥行きに意識が向かない。筐体のコンパクトさを考慮すると、十分音場は広いのだが、立体感がもう一声欲しいという印象。
また、何か突出した個性があるわけではない。すべての要素が高得点な“優等生的サウンド”と言える。これぞまさにモニターサウンドで、そこが魅力であり、多くの人にオススメできるポイントなのだが、一聴しただけでは地味な音と感じる人もいるかもしれない。
ではMAPro1000 IIに切り替えよう。
「藤井風/Prema」の音が出た瞬間に、大幅に音が進化しているのがわかる。冒頭のレトロなエフェクトサウンドや、サビのビートがクリアで、よりクッキリと聴き取れる。
さらに、音が広がる空間が圧倒的に広くなった。特に奥行きの描写が進化しており、ボーカルや楽器の響きが、奥の空間に広がっていく様子が良く見えるようにあった。
中低域も、初代機より肉厚でパワフルになり、グッと音楽の熱さ、美味しさが濃くなった。それでいて、低域はタイトさも維持されており、ボーカルや伴奏の描写を邪魔してはいない。むしろ中高域はよりクリアに、緻密な描写になっている。
絵画に例えるなら、キャンバスそのものが大きくなり、描いている筆先も細くなった印象。しかし、弱い音ではなく、細い筆で描写されるボーカルや楽器の音の1つ1つに、熱気、パワフルさがしっかり備わっており、グイグイと前に出てくる力強さがある。
空間の広さ、情報量の多さ、パワフルさといった要素は、全てを両立させるのはなかなか難しい事なのだが、MAPro1000 IIではそれが実現できている。
YMOの「TIGHTEN UP」も最高だ。細野晴臣のベースがさらに重く、深く沈み込み、躍動感が増す。空間も一気に広がり、小林克也のMCの余韻が、奥の空間にフーっと広がり、消えていく様子もわかるようになった。
冗談抜きに、“狭い部屋が屋外になった”くらいの違いがある。その空間に、個々の音が解き放たれたように広がり、舞い踊っているようだ。
MAPro1000の優等生的なサウンドを、MAPro1000 IIはさらに発展させている。また、ナチュラルでバランスの良いサウンドに、開放感、色気、低域の凄みといった、音楽の魅力をより楽しませてくれる要素がプラスされている。価格は安くなっているのだが、高級イヤフォンのようなオーラも漂うサウンドになっている。
初代の完成度が高かったため、チューニングは大変だったそうだ。音を変化させ過ぎると、「あの音が良かったのに」と言われてしまう可能性があるからだ。そこで、大胆な変更は避つつ、あえて細部のブラッシュアップを積み重ね、「同じ音の延長線上にある進化」を目指したそうだ。
確かにこの音ならば、初めてMAPro1000 IIを聴いた人だけでなく、MAPro1000ユーザーも気に入るだろう。
EDMにマッチするMAPro1000 Drop
MAPro1000 Dropは、型番からわかるように初代MAPro1000をベースにしつつ、EDMに特化させたモデルだ。
EDMに特化させたのは、「MAPro1000のクリアサウンドをベースに、EDMの爆発力や躍動感を楽しめるイヤフォンを作りたい」という要望が、アユートからあったのがキッカケだという。
EDMでは、ハイスピードかつ沈み込む深い低域、重低音の立ち上がりが重要であるため、低域のレスポンスを強化すべく、オーツェイドの「intime翔DD」で採用している高レスポンス型の特別な10mm径ダイナミックドライバーに刷新。
これにより、キレよく細部まで聞き取り易く、さらに深い低域再生を可能にした。そのため、EDMだけでなく、リズム系ゲームや格闘系ゲームにもマッチするそうだ。
高域を5.8mm径RSTが担当しているのはMAPro1000と同じだが、音響チューニングも中低域にフォーカス。EDMのリズムの輪郭がしっかり伝わるよう設計したという。
コンパクトで軽量な筐体もMAPro1000を踏襲しているが、カラーは「Euro Black」となっている。
初代MAPro1000をベースにしたのは、チューニングの自由度が高かったため。特に「勢いとライブ感」を優先してチューニングしたそうだ。内部ハンダは標準仕様でAgハンダではないが、ドライバーの最適化により、高解像度な再生も実現したという。
一方で、利便性の高さはMAPro1000 IIと同レベルに進化させており、ケーブルのコネクターは従来のMMCXから、特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用。信頼性を向上させている。コネクターカバーも左右判別がしやすい新タイプになった。イヤーピースとして「iSep02」と「iFep01」が付属するのも同様だ。
まとめると、MAPro1000 IIが「モニターライクで解像度の高い音」を追求したのに対し、Dropは「リズムとエネルギー感を前面に出したチューニング」になった。音質面では異なる個性を持ちつつ、構造品質、製造精度、信頼性などは同一基準で統一されているわけだ。
MAPro1000 Dropを聴いてみる
MAPro1000 Dropを聴いてみよう。比較相手として、新モデルのMAPro1000 IIと、どちらを選ぶか悩む人が多そうなので、MAPro1000 IIと聴き比べてみる。
まずMAPro1000 IIから、EDMの有名どころとして、「ダフト・パンク/ゲット・ラッキー」を聴いてみた。
MAPro1000 IIは、初代機から空間描写が広大になったので、ビートや手拍子が奥の空間に広がる様子が、よくわかる。低域も深く沈むが、それほど強く主張はせず、縁の下の力持ちとして、音楽全体を下支えしている印象。中域の張り出しもそこまでパワフルではない。
全体として見通しがよく、スッキリとクリアなサウンド。清涼感あって、これはこれで悪くない。
「Avicii/Heaven」や「ZEDD/Clarity」など、広大な空間にリバーブが広がっていくような楽曲も気持ちよく聴ける。ボーカルやSEの響きが伝搬していくフワッとした描写を、芯のあるタイトなビートがキュッと締めることでメリハリが生まれている。
ではMAPro1000 Dropで聴くとどう変わるだろうか?
「ダフト・パンク/ゲット・ラッキー」を再生すると、「うわぁー」と思わず声が出るほど気持ちが良い。MAPro1000 IIに負けじと、MAPro1000 Dropは空間が超広大。ビートは寄り鋭く刻み込まれる。中高域の抜けの良さも手伝い、清涼感もバツグンだ。
「Avicii/Heaven」では開放感がさらに高まる、イヤフォンで聴いているのに「もう外じゃん」と言いたくなるほど、広大な空間で聴いている感覚になる。その空間に、ビートやボーカルの中高域がどこまで広がっていく。あまりの気持ちよさに、つい音量を上げたくなってくる。
特筆すべきは、音場が広大になっても、スカスカな音にはならず、個々の音の力強さは維持されている事。特に中低域はパワフルなのだが、タイトさも兼ね備えているので、パワフルでも、モコモコした不明瞭な低音にならず、切り込むような鋭さと、重さを兼ね備えている。
低音の質は、EDMにおいて一番重要とも言えるので、この部分のクオリティに特にこだわっているのがわかる。
では、MAPro1000 IIとMAPro1000 Dropではどちらが良いかという話になるが、これは「好みや、よく聴く楽曲による」だろう。
MAPro1000 Dropは、音の質感がやや硬質で、鋭いため、ジャズやクラシックなど、アンプラグドでウォームな楽曲が好きならば、MAPro1000 IIの方が良いだろう。
一方で、EDMだけでなく、例えばJ-POPでも米津玄師やYOASOBI、Vaundyなど、打ち込み系の楽曲が多いアーティストを聴くなら、MAPro1000 Dropの方がハマるかもしれない。欲を言えば、両方買って気分で使い分けたくなる。
有線イヤフォンが再評価される今だらこそ、聴いて欲しい
正直に言って、MAPro1000の時点で、「手頃な価格で、装着感も良く、音も万能サウンドで何も文句がないよく出来たイヤフォン」を実現しており、進化の余地はあるのかな?と思っていた。だが、MAPro1000 IIで「万能サウンド」をさらに前進させ、さらなるクリアさ、音場の広さ、低域の美味しさを獲得し、「MAPro1000 IIで聴きたい」と思わせるサウンドを実現したのは見事だ。
しかも、「進化したので価格もアップしました」が当たり前の時代に、13,200円と低価格化してくれたのは「ありがとう」と言うほかない。以前にも増して、多くの人に「とりあえずMAPro1000 II買っておけば間違いない」とオススメできるイヤフォンになった。
音楽ジャンルに特化させるMAPro1000 Dropという新たな楽しみも登場した。こちらも14,300円なので、MAPro1000やMAPro1000 IIが気に入ったら、ぜひ聴いてみて欲しい。好みに合わせてイヤフォンを選びやすいのも、価格を抑えてくれたからこそだ。
Maestraudioは以前、弦楽器の再生に特化した「MA910SRDC」というイヤフォンも開発しており、今回のEDM向けのMAPro1000 Dropは、それとはまったく異なる方向性のイヤフォンを実現してみせた。
今後は「アコースティック・ジャズやボーカル特化といった“人の声や楽器の息づかい”をより自然に表現できるモデルに挑戦したい」としている。こちらも非常に楽しみだ。
完全ワイヤレスイヤフォンが当たり前になった昨今だが、それにより、音質を純粋に追求し、末永く愛用できる有線イヤフォンの魅力が再評価され始めている。完全ワイヤレスからポータブルオーディオに興味を持ち、有線イヤフォンを試してみたいという人も多いだろう。
そんな時はぜひ、MAPro1000 IIとMAPro1000 Dropを聴いてみて欲しい。有線イヤフォンの魅力を存分に堪能できるはずだ。