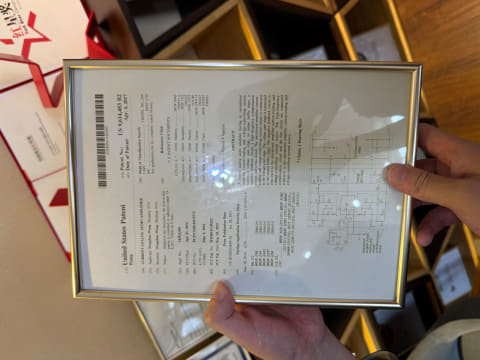藤本健のDigital Audio Laboratory
第1035回

iPhoneでaptX/LDAC使えるトランスミッターを開発した「Questyle」とは?
2025年8月25日 08:23
日本のオーディオメーカーが少なくなっている中、ベンチャーを中心とした中国メーカーの勢いは止まらない。どうせ2流、3流だろ……と思っている人も少なくないが、機能面、性能面、そして技術面においても、世界トップレベルになってきており、とくにポータブルオーディオの世界では、中国勢に追いつくこともだんだん難しいところになってきているように思う。もちろん、これはオーディオの世界に限ったことではないが、勢いにのっていることは間違いない。
数々の中国メーカーがある中、個人的に注目している企業の一つが中国・深センにあるQuestyle(クエスタイル)だ。2012年設立で、日本への参入は今回が3回目という同社は、今回の進出のタイミングでユニークな機材「QCC Dongle Pro」および「QCC Dongle」を世界に先駆け日本マーケットに投入した。
この製品については発売前に、この連載でも取り上げているが、アップルの認証であるMFiを取得しつつ、QualcommのSnapDragonを搭載し、さらにソニーのLDACに対応させるなど、日米の大手メーカーとしっかり連携しているのもユニークなところ。その結果、発売後は入荷のたびにすぐ品切れになる大ヒット製品となっている。
一方、数多くの国際特許を取得した技術で開発したヘッドフォンアンプも発売するほか、今秋~冬にはワイヤレスオーディオの世界をあっと言わせる新製品、新技術の投入も計画中という。
なぜ、深センのベンチャー企業にそれだけの勢いがあるのか、その深センに行って、Questyleの創業者でありCEOである王豊碩(ワン・フォンシュオ)氏に、いろいろ話を伺ってみた。
7歳の少年が作った「ウォークマン」:すべてはここから始まった
――王社長の音響への情熱は、いつ頃から始まったのでしょうか?
王氏(以下敬称略):小学校1年生、7歳の時でした。当時、日本のソニーのウォークマンやディスクマンに出会って、この素晴らしいものに夢中になったんです。でも、父は工場を経営していて、それなりに財力はありましたが、とても厳しくて「無駄なお金は使うな」という方針で、お小遣いをもらえず、こうした機器を買ってくれることはありませんでした。
――それで、どうされたんですか?
王:買えないなら自分で作ろう、と考えたんです。父の工場にはいろいろな工具や測定器があったので、弟と一緒に雑誌を読んで部品をかき集め、乾電池を何本も使って自分でカセットテープの音楽を流せる装置を組み立てたのです。
――7歳で、ですか!
王:結構大きな機材ではありましたが、学校に持って行ってみんなの前で音楽を流したら、みんな驚いていました。その時から、私は“ウォークマン”と呼ばれるようになったんですよ(笑)。
王氏の生まれ故郷は江蘇省の美しい山間部だが、中学校になると電子市場をよく回るようになった。そこで運命的な出会いが待っていた。
王:ある日、元軍人で無線通信兵だった方が個人で営む修理センターを見つけました。その方が自分で作ったハイファイ装置から流れてくる音を聴いて、「この音は何ですか?」と尋ねたら、「これがHi-Fiだ」と教えてくれました。その瞬間、私も絶対にHi-Fiを作りたいと思ったのです。
――そこから本格的な勉強が始まった、と。
王:その方にお願いして、部品を全部そこで買う代わりに、毎日1~2時間、技術書や雑誌を読ませてもらいました。本を買うお金がないので、手書きでノートに写していたんです。20冊以上のノートを作りました。
――20冊!それは大変な作業ですね。
王:家に帰って自分で回路を組み立てていると、よく母に見つかり「勉強の邪魔だ」と取り上げられ、捨てられました。それで夜中にこっそりゴミ箱から取り戻して、また作り直すのです。何度も何度もそれを繰り返しました。
このころから既に、王氏の音響への情熱は並々ならぬものがあった。高校時代には、クラスメイトのテープデッキやディスクデッキを改造して音質を向上させ、お小遣いを稼いでいたという。
大学時代の大発明:オーディオ界を変えたCMA技術の誕生
――大学では電子工学を専攻されたんですね。
王:揚州大学で電子工学を学びました。大学2年生の時、ちょっとした面白い出来事がありました。
私はひどい近眼で、一番前の席に座っていたのですが、アンプの回路を組み立てる実習において、先生が部品を一番後ろの人に配り終わる前に回路を完成させてしまったのです。
先生は、「それは前のクラスの学生が作ったものだろう」と不審に思われたのですが、目の前で再度組み立てて見せると、今度は実験室の手伝いをしてくれと言われ、ここでアルバイトをするようになりました。さらに当時の中国の教育方針であった、素質教育というものが大きな後押しになったのです。
――素質教育?
王:当時、中国では学生たちが「勉強以外のことができない」「教科書通りのことしかできない」ということが大きな社会問題になっていました。そこで実際に手を動かし、いろいろなことを実践できるようにしようという風潮になっていたのです。
そんな中、バイト先となった先生の計らいもあって、専用のイノベーション研究室の責任者に任命してもらい、その研究室の設備をすべて自由に24時間使えるようになりました。
そのイノベーション研究室をベースに、3人の仲間と共に、電流モード増幅(CMA:Current Mode Amplifier)技術の研究に没頭しました。2年間は夏休みも実家に帰らずに実験室にこもって開発を続けました。
――CMA技術とは、具体的にはどのような技術ですか?
王:従来のアンプは電圧の変化で信号を処理しますが、CMAは電流モードで信号処理を行ばいます。
電圧モードでは高いインピーダンスが必要で電力消費も大きいのですが、電流モードは低インピーダンスで高速処理が可能です。電流が流れているかどうかで0と1を判定するため、電圧が低くても問題なく、結果的に消費電力を大幅に削減できのです。
――なるほど。それがUSBバスパワーでも高性能を実現できる理由ですね。
王:その通りです。トランジスタは本来、電流モードのデバイスなのです。ただ、電流モードで回路を設計するには、バランスを対称的に保つ必要があり、製造技術上の課題もありました。私たちはそれらの課題を解決し、小型部品での実装を可能にしました。
――技術的なブレークスルーがあったということですね。
王:一般的なアンプでは、USB電源のような微細な電力では大型ヘッドフォンを駆動するのは困難です。しかし、CMA技術なら同じ電力でもはるかに効率的に駆動できます。これが、私たちのM15やM18がUSBバスパワーだけで高インピーダンスヘッドフォンを鳴らせる秘密です。
――2005年の学術発表について詳しく教えてください。
王:中国の国家レベル学術誌「電子技術」に第一著者として論文を発表しました。
この雑誌は1977年から続く権威ある学術誌で、中国の音響技術分野では最高レベルの学術機関です。当時、大学3年生が国家レベルの学術誌に筆頭著者として掲載されるのは極めて異例でした。
――その技術は特許も取得されているのですか?
王:はい。中国国内の発明特許はもちろん、PCT国際特許、アメリカの特許も取得しています。
王:2014年にアメリカで特許を取得したので、いま10年が経過しましたが、あと約10年は有効です。競合としてはKRELLがCAST(Current Audio Signal Translation)という異なる方式の電流モードを使っていますが、彼らは大型の据え置き機器向けで、私たちとは用途が全く違います。私たちは小型のポータブル機器としての実装に特化しています。
――SiP(System in Package)化についても教えてください。
王:初期のCMA回路は部品点数が多く、サイズも大きくなりがちでした。そこで、SiP技術を使ってCMA回路を一つのパッケージに集積することで、大幅な小型化と効率化を実現しました。
これにより、QCC Dongleのような手のひらサイズのデバイスにも、デスクトップ機器に匹敵するCMA技術を搭載できるようになったのです。
――製品名の「M12」「M15」「M18」という数字にも意味があるそうですね。
王:実は、2005年の技術発表から何年経ったかを表しているのです(笑)。
M12は2017年、M15は2020年、M18は2023年に発売しました。ある時ウイスキーを飲んでいて、「○○年もの」という表記を見て思いつきました。自分の核心技術への記念として、この命名ルールを採用しています。
――つまり、現在でもCMA技術が進化を続けているということですね。
王:その通りです。基本原理は2005年から変わりませんが、回路設計や実装技術は常に改良を重ねています。最新のSIGMAシリーズでは、SiPカレントモードアンプがさらに進化し、より小型でありながら、これまで以上の性能を実現しています。
私は「30年以上アナログ回路に携わってきた」と言えるほど、この分野に情熱を注いできました
O2Microでの修行時代:アメリカ人ボスとのラーメン談義
大学卒業後、王氏はNASDAQ上場企業の「O2Micro」に就職。アメリカ本社での研修を経て、深セン勤務となった。
王:当時のボスはNSC(National Semiconductor)出身の日系アメリカ人でした。彼はNSC時代、パワーアンプICのLM1875やLM1976、LM3886などを開発したスーパーエンジニアであり、プライベートジェットを5機も持っているすごい人なのですが、いろいろ指導を受けました。
私のCMA技術に興味を持ってくれ、アドバイスもいただきましたね。私の出身地は麺で有名なところで、ボスも日本食が好きだったので、よく一緒にラーメンを食べに行きましたね(笑)。
――O2Microではどんな仕事を?
王:最初はFAE(フィールド・アプリケーション・エンジニア)として、主にAppleやFoxconnといった顧客のサポートを担当していました。電源管理ICやオーディオICの設計に携わっていました。
深センの電子産業の活況を目の当たりにした王氏は、2008年から深センに腰を据えることになる。そして2012年、30歳の誕生日に人生の大きな決断を下す。
王:ボスに「会社を辞めたい」と伝えた時、「給料が足りないのか、仕事がきついのか」と聞かれました。「いえ、CEOになりたいんです」と答えたら、「それなら私にはもう何もできない」と言われました(笑)。
2012年12月12日:Questyleの誕生
――なぜ2012年12月12日という日付を選んだのですか?
王:12という数字が私にとってラッキーナンバーなのです。私の製品も12から始まっていますし、CMA技術を発表したのも2005年の12月でした。
――Questyleの創業当初は何人体制でスタートしましたか?
王:5~6人から始めて、2013年~2014年には14人程度の規模になりました。ありがたいことに、創業時から10年以上在籍しているコアエンジニアがまだ何人もいるんです。現在は約40人の体制になっています。
王:昔はKENWOODやパイオニアなど、日本メーカーの大きなステレオを使っていました。でも、2012年という時代は、そうした大きなステレオではなく、Hi-Fiのヘッドフォンで聴くのが流行ってきていました。
自分の技術を使って、DACやヘッドフォンアンプを作ったら世の中に受け入れられるのでは?という思いもあって、Questyleを作ったのです。
でも、なぜ最初の製品を「CMA800」という名前にしたかというと、当時私はSennheiserのHD800というヘッドフォンを持っていました。とても高価なヘッドフォンでしたが、市販のアンプでは満足のいく音が出せなかったので、自分で作ってみたのです。
王:結果的に、いまのフラッグシップモデルである「CMA Eighteen」などにつながる技術の基盤になりました。
――満足のいく音質にするためには、どうしていますか?
王:私はSennheiser HD800のような高級ヘッドフォンをリファレンスとして使用しています。音の広がり、定位、解像度、そして音楽的な表現力を最大限に引き出すよう、CMAアンプの特性を細かく調整しています。
時には、わずかな部品の変更や回路の調整が、音質に劇的な変化をもたらすこともあります。こうしたことの積み重ねでオーディオ機器としての性能を向上させていくのです。
その後Questyleは高品位なポータブルオーディオプレイヤーやUSB-DAC、ヘッドフォンアンプなど、ポータブルオーディオに特化した高品位なオーディオメーカーとして次々と製品化。アメリカ市場、ヨーロッパ市場、そして日本市場とさまざまなマーケットへ展開していった。
日本市場への「本気」の挑戦:なぜQCC Dongleは日本先行だったのか
――Questyleとして、日本市場についてはどのようにお考えですか?
王:日本、アメリカ、ドイツは「技術的な成熟市場」だと考えています。中でも日本市場は、製品の細部まで厳しくチェックし、わずかな欠点も許容しない厳しい目を持っています。
O2Micro時代のボスから「日本は世界で最も厳しい市場で、品質に問題があると、すぐに飛行機で現地に飛んで8時間も会議室に缶詰にされる」と教わりました(笑)。
――それでも、あえて日本市場に挑戦される理由は?
王:真に優れた製品であれば、この厳しい日本市場で必ず成功できると信じています。日本での評価は、世界での評価に直結すると考えているのです。
Questyleは2015年からfinalと提携して日本市場に参入。それなりの実績を上げてきたが、コロナ禍に入りさまざまな事情から提携は終了。その後、深センの若者が個人貿易レベルで販売を試みたが、本格的な展開には至らなかった。
王:QCC Dongleを世界に先駆けて日本で先行発売したのは、1年前に藤本さんとお会いした際、プロトタイプを見て「これが面白い」と言っていただいたのが大きなキッカケとなっています。そして、「世界で最も厳しい日本市場で成功すれば、どこでも通用する」という確信があったからです。本気で挑戦したかったのです。
QCC Dongle誕生秘話:iPhoneユーザーの個人的な不満から
――QCC Dongleの開発はどのような経緯で始まったのですか?
王:実は、私自身の個人的な不満から始まりました。iPhoneを愛用しているのですが、AACの音質にどうしても物足りなさを感じていました。
高級ヘッドフォンをワイヤレスで手軽に使いたいと、ずっと考えていたのです。ご存じのとおり、高級ヘッドフォン、イヤフォンであれば、aptXやaptX Adaptive、aptX Lossless、またソニーのLDACなどに対応しており、高品質な音で鳴らすことができます。
しかしiPhoneでは、これらのCODECに対応していないため、SBCかAACしか使えない。なんとかならないか?と。
――それはいつ頃のことですか?
王:2022年後半から考え始めていました。当時、M18iのような製品で有線接続すると確かに高音質なのですが、常にケーブルを持ち歩くのは不便でした。Boseのようなワイヤレスヘッドフォンも試しましたが、AACでは音の細かいディテールが失われてしまいます。
――技術的な実現性はすぐに見えましたか?
王:Qualcommとは以前からプレイヤーでSnapdragonチップを使っていた関係があったので、技術的には「絶対にできる」と確信していました。また、ソニーとも以前からLADCのライセンス契約をしていたので、これも利用できるはずだ、と。
QCC DongleにはSnapdragon QCC5181というチップを使っています。送信と受信の両方に対応できる優秀なチップです。実際の開発にかかったのは約9カ月でした。2024年第4四半期に開始して、今年5月末にまずQCC Dongle Proを、さらに6月にQCC Dongleを、それぞれ日本で先行発売しました。
――日本発売後の反応はいかがでしたか?
王:正直に言うと、毎日とても緊張していました(笑)。ちょうどNintendo Switchが発売されたばかりで在庫がない時期で、スタッフが前日から店に並んで入手し、予約して店舗まで持参してゲーム機での動作確認をしたこともあります。お客様からのフィードバックには迅速に対応し、ファームウェアのアップデートを重ねました。
確かに製品開発期間は約9カ月でしたが、App開発、クラウド連携、ファームウェアの最適化など、すべてを一から構築する必要があり、結構なハードワークになりましたね。
ワイヤレスオーディオの「その先」へ:この秋に発表される革新技術
インタビューの最後に、王氏は興味深い話を聞かせてくれた。
――QCC Dongleの次は、どのような展開をお考えですか?
王:現在、ワイヤレスオーディオの常識を覆すような技術を開発中です。Bluetoothは圧縮による音質劣化が避けられず、Wi-Fiも遅延や干渉の問題があります。私たちが開発している技術は、極めて低い遅延で、膨大な量のオーディオデータを非圧縮で伝送することを可能にします。
――具体的にはどのような技術なのでしょうか?
王:今はまだ詳細をお話しすることはできませんが、この秋には発表予定です。この技術により、192kHzのハイレゾ音源を遅延ほぼゼロで伝送できるようになります。ゲームやVR/ARといった分野でも、その真価を発揮すると確信しています。
最終的には、QCC Dongleのような中継機器も不要になり、スマートフォン単体で真のロスレス・ワイヤレスオーディオを実現できるようになるでしょう。
王氏の言葉からは、現在のワイヤレスオーディオの限界を根本的に解決する、画期的な技術への強い自信が感じられた。
「全電路無損の信号処理」を貫く技術者の哲学
長時間におよぶインタビューを通じて、王豊碩氏の人生は一本の線で繋がっていることがよくわかった。7歳でテープデッキを自作した少年が、30年の歳月を経て世界レベルの音響技術を生み出し、さらにその先の未来を見据えている。
Questyleが掲げる「全電路無損の信号処理」という哲学は、単なる技術論ではない。音楽を愛するすべての人に、設備の制約なく、いつでもどこでも最高の音楽体験を提供したいという、一人の技術者の純粋な想いが込められている。
この秋に発表される「革新的なワイヤレス技術」が、どのような驚きを私たちに与えてくれるのか。ワイヤレスオーディオの未来を切り拓くQuestyleの挑戦から、これからも目が離せない。